
こむらがえりが治らない!?原因と予防法、上手な対処法とは?柔道整復師が解説
公開日: 最終更新日:
睡眠中や運動中に突然、足がつった経験がある方は多いのではないでしょうか。この「足がつる」というのが、「こむらがえり」という現象です。そんな誰しもが経験したことがあるこむらがえりですが、なぜ治らないのか、その原因と予防法、対処法について専門である柔道整復師がお伝えします。
※尚、文中にご紹介している商品は、アフィリエイト広告を利用しています。
Contents
こむらがえりとは
こむらがえりとは、
“有痛性筋痙攣“
「ゆうつうせいきんけいれん」といい、ふくらはぎに起こることが多いですが、ふくらはぎに限定したものではなく足の裏や指、太もも、すね、足の甲などにも起こる現象です。
こむらがえりは年齢とともに重症化したり、症状が慢性化しやすいとも言われています。
こむらがえりが治らない原因
こむらがえりが治らない原因について見ていきましょう。
こむらがえりを放置している
こむらがえりはそのまま放置していると数十分間も治らないこともあります。こむらがえりの対処法を知らなかった患者さんは30分もつったままで、大変つらい経験をされました。きちんとした対処法をしていれば、こむらがえりは数秒で治りますが、適切な対処をしないと肉離れになる恐れもあるため、正確な知識を深めていただければと思います。
放置せずにストレッチのようにゆっくり伸ばしましょう。
ストレッチの方法については後ほどご紹介します。
疲労
若い世代に多いのが、テニスやサッカー、バスケなどの走る、止まる、ジャンプ動作を多く行うスポーツによる筋肉疲労です。運動中や運動直後にこむらがえりが起こりやすい方は、筋肉疲労が原因かもしれません。また、中高年になると少しの運動でも筋肉疲労を起こしやすくなります。「頭ではそんなに動いていないつもり」でも「身体はしっかりダメージを受けている」ために、頭と身体のギャップが身体の不具合、こむらがえりとなって現れるのです。
ケガの予防の含めて、セーブしながらスポーツを楽しんでくださいね。
疲労と関連して、足のつき方が良くないと効率の良い出力が出せないので、無理な力が必要となり、筋肉疲労を早めてしまいます。
代表例が扁平足(へんぺいそく)や内反足(ないはんあし)です。
この場合にはインソールなどで対策をすると良いでしょう
インソールについてはこちらをご覧ください。
水分不足
長時間のスポーツで大量に汗をかいて脱水状態になると、こむらがえりが起こりやすくなります。夏にこむらがえりが多いのも水分が関係していると考えて良いでしょう。水分不足になると筋肉が縮み過ぎるのを防ぐ腱紡錘(けんぼうすい)の機能が低下して、筋肉が異常に収縮することが原因だと言われています。
喉の渇きを感じる前に水分補給は必要です。
夏場では15分に一度、口に含む程度の量を摂取しながら運動をしましょう。
冷え
ふくらはぎは「第二の心臓」とも言われ、全身の血行を巡らせる役割があります。しかし、冷えによってふくらはぎの筋肉が緊張すると、血行不良を起こしこむらがえりが起こりやすくなるのです。
冬場の気温の低下だけでなく、夏場の夜間のエアコンや扇風機の風がによる冷えもこむらがえりの原因となります。
冬の時期の保温には、レッグウォーマーや靴下を履いて寝るなどの冷え対策をしましょう。
カリウムやマグネシウムの不足
カリウムやカルシウムは神経の伝達や筋肉の収縮をスムーズにする働きがあり、この2つを調整しているのがマグネシウムです。3つはミネラルと呼ばれ、ミネラルのバランスが崩れると筋肉が痙攣しやすくなりこむらがえりが起こります。
普段意識して摂取するものではないので、出来るだけ不足しないような献立やサプリが必要です。
肝臓の疾患
肝臓の疾患の中でも、とくに肝硬変でこむらがえりが起こりやすくなります。肝硬変になると、筋肉を維持するためのカルニチンという物質が不足し、筋肉に痙攣が起こりやすくなるのです。
治療と並行して、こむらがえり予防に努めましょう。
糖尿病
糖尿病によって血糖値が高い状態が続くと末梢神経に小さな傷がついて刺激が起こり、傷ついた神経の刺激が筋肉に異常な信号を送ると、過剰に筋肉が収縮してこむらがえりが起こりやすくなります。糖尿病が原因のこむらがえりは、明け方や安静時に起こることが多いのが特徴です。
普段からの糖質の摂りすぎには気をつけましょう。
妊娠中
妊娠中はお腹が大きくなることで足への負担も大きくなり、筋肉が疲労しやすくなるのでこむらがえりが起こります。また、ホルモンバランスが崩れることで血流が悪化すること、カルシウムやビタミンDが不足することなども関係しているのもこむらがえりを起こす要因の一つでしょう。
妊娠中は何かと身体の変化が起きやすいものです。
下記の記事も参考にご覧ください。
→妊婦さんの腰痛はマッサージで対応!その方法と腰痛の原因も解説!

こむらがえりの治し方
こむらがえりの治し方を見ていきましょう。こむらがえりは筋肉が硬直する現象ですので、筋肉を伸ばすようにゆっくりストレッチを行うとその場で治ります。
ふくらはぎにこむらがえりが起きたときには、
アキレス腱伸ばし

または座った状態で膝を伸ばしてつま先を手で掴む。

太ももの前のこむらがえりには、足首を持って太ももの前を伸ばします。

太ももの裏のこむらがえりには、膝を伸ばして前に体を倒します。

太ももの裏のこむらがえりが起きて、立てない時には座って膝を伸ばして、つま先をつかみましょう。
(※ふくらはぎのストレッチと同じです)
症状が治まったら蒸しタオルなどでふくらはぎを温め、じっとしているよりも少しだけ歩いたりしましょう。
運動の場面でこむらがえりになると動けなくなってその場に留まってしまい、誰かにおんぶされて移動することがありますが、これはNGです。
出来るだけその場でこむらがえりをストレッチで落ち着かせてから、自分の足で歩きましょう。
おんぶして歩いたときの衝撃がまたこむらがえりのきっかけとなってしまうのです。
【その場でこむらがえりを抑えて、自分の足で歩く】
これがポイントです。

こむらがえり予防のためにできること
こむらがえり予防のためにできる4つのことをご紹介します。ただし、効果には個人差があるのでさまざまな方法を試してみてください。
食事
こむらがえりを予防するには、栄養バランスのとれた食事を心がけることが大切です。とくに、筋肉疲労の改善に役立つビタミンB1やカリウムなどが含まれた食材を積極的に食べるのがおすすめです。たとえば大豆製品や魚、牛肉、鶏肉などは、血流を良くして体を温めてくれます。
夏場の場合には、朝食のお味噌汁を少し濃い目にするなどして塩分不足を補いましょう。
食事についてはこちらも参考にご覧ください。
→健康に気を使う人必見!健康にいい食べ物に含まれている栄養素とは?
疲労回復
こむらがえりは筋肉疲労で起きやすいため、運動後のケアは必ず行いましょう。運動後のストレッチと十分な睡眠を心がけ、体に疲労を残さないことが大切です。
そして入眠後3時間が成長ホルモンの分泌が最も活発と言われています。
身体の成長と疲労回復には欠かせない成長ホルモンですので、睡眠環境の整えにも意識してみてましょう。
成長ホルモンについてはこちらをご覧ください。
漢方薬
こむらがえりには、「芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)」という漢方薬が効果的です。筋肉の緊張や痛みを和らげる作用があり、服用から平均6分で効果が現れると言われています。
価格と内容量の面から考えて、継続的に摂取するのでしたらこちらがオススメです。
加えて粒状になっているのも飲みやすくて良いでしょう。

【第2類医薬品】「クラシエ」漢方芍薬甘草湯エキス顆粒 45包
次にお試しで使ってみるなら、安価なものということでこちら。
正直このような商品は、価格に比例して内容物に差があるといっても過言ではありません。
「安かろう、◯かろう」ではありませんが、出来るだけ質の高いものを摂取した方が良いでしょう。
サプリ
運動中や睡眠中など、人はあらゆる場面で汗をかきます。汗や尿によってミネラルが体外に排出され、ミネラル不足に陥ってこむらがえりが起こりやすくなるので、サプリでカルシウムやマグネシウムなどのミネラルを補うことでこむらがえりを予防できます。
手軽に継続的に摂取するならこちら。

ディアナチュラ カルシウム・マグネシウム・亜鉛・ビタミンD 180粒 (30日分)
内容量も比較的マグネシウムや亜鉛が多く含まれています。
そして、汗の出る量が多い方はこちらでカリウムを多く摂取しましょう。

レバンテ カリウム サプリ プレミアム [ 塩化カリウム 業界最高水準 1200mg ] 栄養機能食品 (ビタミンB1 B2 B6 B12 E) レスベラトロール 和漢 270粒 30日分 日本製
汗と一緒にカリウムは排出されてしまいますので、夏場に足がつりやすい方は意識して多めにカリウムを摂取しましょう。
ただし、人工透析を受けている方はカリウムの過剰摂取にならないように注意が必要です。
こむらがえりについての疑問集
ここからはこむらがえりについての疑問集にお答えしていきます。
こむらがえりに薬はいいの?
こむらがえりには薬での対処も有効です。
コムテクトは水が無くてもその場で飲めるため、大変重宝するでしょう。
スポーツやハイキング、登山など、足に負担のかかる際には携行してみてはいかがでしょうか?
こむらがえりの痛みが残る時の対処法は?
こむらがえりの痛みが残る時の対処法には、
- ストレッチ
- 温める
- 先生による施術
が挙げられます。
筋肉への対処法といえば、マッサージを思い浮かべるかともいますが、こむらがえり時のマッサージは禁忌です。
専門的知識のある先生が行うケースでは良いですが、知識がないままに行うと痛みは強くなるでしょう。
ストレッチは強く伸ばすと肉離れのリスクがあるため、ゆっくり気持ちよさを感じながら行います。
温めることでは血流が促進され、リラックス効果もあり、筋肉の弛緩と新鮮な栄養と酸素の供給にはとても効果的です。
それでも痛みが長引く場合には、先生の施術を受けることが望ましいでしょう。
ストレッチを上手に行う方法についてはこちら。
→間違ったストレッチをしないために、知っておくべきこととは?
こむらがえりの後、歩けないのはなぜ?
考えられるのは、
- こむらがえりの余韻で痛みが残っている
- また筋肉が痙攣している(再びこむらがえりが起きそう)
- 筋繊維を傷つけているため、痛みで歩けない
が挙げられます。
こむらがえりの後すぐに歩くと、再び起きやすいため、初めは慎重に歩きましょう。
数分間、歩けない状態が続いても問題ありませんが、それ以上となると筋繊維を傷つけたかもしれません。
包帯やテーピングなどで固定した後、先生の施術を受けましょう。
テーピングの効果を活かすにはこちらをご覧ください。
→テーピングの効果って?効果を最大限活かすための注意点と疑問アレコレ
ふくらはぎのつる痛みは肉離れ?
ふくらはぎのつる痛みと、肉離れの症状は違います。
ただ症状だけで明確に両者を判断するのは、確実ではありませんが、肉離れではつる症状は起きませんので、こむらがえりを考えて良いでしょう。
肉離れが起きやすい状況としては、「つる」という状態で運動すると肉離れが起きやすいです。
つた状態で動くことは肉離れの前兆を捉え、無理な運動は控えた方が賢明でしょう。
肉離れについて詳しくはこちら。
→肉離れの治療期間は?症状別に治るまでの期間や早く治すコツをご紹介。
こむらがえりの痛みが長引くのは?
こむらがえりの痛みは数分から数時間、または翌日まで続くことも珍しくありません。
それは筋肉に起きている状態によって様々です。
- 数分間:筋肉の痙攣状態が完全におさまっていない
- 数時間:筋肉に筋肉痛程度の損傷が起きている
- 翌日:軽度の肉離れが起きている
厳密に言えば、筋肉痛はごく軽度の肉離れに相当します。
なかには翌日になると歩くだけでも痛い、という患者さんもいらっしゃいます。
そのようなケースではストレッチの仕方が少し強かったと考えるのが妥当でしょう。
くれぐれも伸ばすときは「ゆっくりと…」
【まとめ】こむらがえりが治らないについて
こむらがえりは、適度な運動やストレッチ、バランスのとれた食事など普段の生活を少し意識するだけで予防できるものがほとんどです。まずは、自分のこむらがえりの原因を知り、今回紹介した予防法を試してみましょう。それでも症状が改善しない場合は、一度医療機関を受診するのがお勧めです。
カテゴリ:脚の痛み
タグ:こむらがえり,ストレッチ,マッサージ,予防,原因,栄養,水分不足,温める,疲労,筋肉痛,糖尿病,肉離れ,肝臓,運動,食事
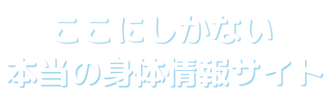



 変形性股関節症でしてはいけないこと、運動療法や手術を詳しく解説!
変形性股関節症でしてはいけないこと、運動療法や手術を詳しく解説! テ二スボールを使ったマッサージ10選!コリを解消する方法をご紹介!
テ二スボールを使ったマッサージ10選!コリを解消する方法をご紹介!













